こんにちは、おのやまです。
中学で不登校になってしまった長女がおり、現在は定時制高校に通っています。中学2年の夏休み明けから学校に行けなくなり、適応指導教室に通うようになりました。
適応指導教室では自主学習のみになるため、毎日学校に通い授業を受けている同級生との間には自然と学力の差ができてしまいます。
その差を可能な限り埋められないだろうかと様々な学習方法を探し、検討したものや実際試してみたものをご紹介します。
個別指導塾
メリット
- 子供の学力に対応したカリキュラムを独自に組み、きめ細やかな指導が可能
- 教師1人:生徒1~2人なので集団が苦手な子供でも安心
- 教師との相性による変更や学習時間帯などの融通が利く
デメリット
- 費用が高額
学習形態が理想的だったので資料をいくつも取り寄せて検討しましたが、生徒1人に掛かるコストが大きいため料金もそのぶん上がってしまうのはどこも同じようでした。
金銭面に余裕があればぜひ候補に入れたいところです。
家庭教師
塾へ行くために外へ出ること、学校の友達に会いたくないなどの理由から家庭教師も候補のひとつとして考えることができます。昔ながらの自宅に先生が来て勉強を教えてくれるというスタイルから、オンラインで一対一の授業が受けられるなど選択の幅が広がってきており、ハードルも低くなっています。
派遣
メリット:日時や教科、相性による教師の変更はセンターを通して行うことができる
デメリット:事前に来客用の準備をしたりなど気をつかう、感染症の不安
家庭教師センターが所属している教師を家庭に派遣します。
体験授業を申し込み、自宅に来たのはセンターに登録している大学生でした。接し方、教え方がとても上手く、長女も興味を持ったのでこの人にお願いしたいと思いましたが、実際担当するのは他の教師とのことでした。他にも受講料以外に費用が掛かるケースがあるので注意しましょう。
個人契約
メリット:事前に面談をして人柄を見ることが出来る、取り決めた費用以外かからない
デメリット:個人契約になるため子供との相性による変更や、トラブルへの対応が難しい
こちらは完全に個人間での契約になります。
教師と家庭を繋ぐサイトに登録しお互いの条件が合ったら面談、といった感じでした。
オンライン
メリット:自宅で個別指導が受けられる、費用が低額
デメリット:環境に左右される、機器トラブルなどで授業時間が削られる

わが家はwifi使用可能、ノートPC(カメラ、マイク機能つき) ・ペンタブレットありの環境です
長女が申し込んだ体験授業は40分で教師は男子大学生、モニターに映った数学の問題を一緒に解いていきました。映像とマイクでやりとりをしながらペンタブレットで双方から同時に書き込めるので、対面でのやりとりよりも利便性が高いと感じました。
非接触で個別指導が受けられるのに加え、1コマの授業料が他の学習方法と比べてかなり安く魅力的です。専用の教材を使用する場合でも自宅のプリンターで出力できるので実費は掛かりません。
現在はオンラインによる授業を取り入れている学校もあり、今後もリモートワークという働き方が浸透していくことを考えるとある程度こうした環境で慣れておくのも良いと感じました。
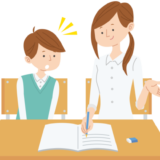 家庭教師を選ぶ時におさえておきたいポイント
家庭教師を選ぶ時におさえておきたいポイント
映像授業
長女の通う学校では「自学自習システム」というインターネットで映像授業とデジタル問題集を無料で使えるサービスを取り入れていました。小・中学校で習う内容を各単元ごとに分からない箇所を動画を使って確認できるので、分からないところをピンポイントで理解するには有効な学習方法です。
CMで流れているほんの数秒の映像授業に思わず引き込まれてしまうように、何となく見るだけのつもりが最後まで見てしまったという嬉しい現象にも期待できそうです。
地域の学習支援
子供食堂の主催をしている方とお話する機会があり、長女の不登校の話をしたところ学習支援も行っているということで中学校を卒業するまでの間、週1回勉強を見てもらっていました。
フードパントリーにも利用されている地域の寄合所で、行ける時だけ行く、という参加でしたがこの気軽さも良かったようです。近隣の小中学生が来ている時もあり、先生がまとめて指導していました。
母子家庭、不登校等事情のある子供だけみているとのことで学習支援をしていることは公にしていなかったそうです。ネットや市報等に掲載されない情報もあるので機会があれば調べてみましょう。
ドリルの購入
長女と二人で本屋に行き、中学1~3年生までの英語と数学、その他に国語、地理、歴史、理科のドリルを揃えました。左側が解説、右側が問題を解くページになっており、フルカラーで図解も多く親しみやすい内容です。
その後、学習支援の先生に勧められたドリルを使って学習するようになりました。
先生にお勧めされたドリルは中学校で使用する教科書の出版社ごとに作られており、学校の授業内容を学習できます。新たに中学1~3年生までの英語と数学を購入しました。
単色でイラストもなく、本当に教科書の一部っぽいデザインでしたが、返ってそれが余計な情報に目を奪われず集中しやすいようにも感じられました。
このドリルは適応指導教室にも持って行くようになりました。
結果としては先生のお勧めで購入したドリルで勉強し、本人が最初に選んだドリルも5教科をカバーしていたので受験直前の勉強に役立ちました。
長女が使いこんでいたのは英語と数学です。
英語と数学は積み重ねの教科です。学ぶほど知識が増え解ける問題も多くなり、それらが自信に繋がっていったのではないかと思います。

ドリル選びはプロと本人におまかせ!
自主的に勉強することの難しさ
目的がないものに対して意欲を高めるというのは難しいことです。目指すものがない状態では何から手を付けていいのかすら分かりません。周りが単に勉強しろと言うのはゴールのない道をとにかく走れと言っているようなもので、やる気は減退する一方です。
家での勉強が思ったようにできず一時は進学を諦めていた長女ですが、不登校でも行ける高校があることを知り受験することを決めました。
志望校が決まった秋からは伸ばせる教科に力を入れ、自ら進んで勉強するようになっていました。
本腰を入れた受験一ヶ月前~直前まで本当によく頑張っていたと思います。
目標を見つけることは、意欲に直結する重要なことなのだと気付かされます。
勉強は高校に進学してからのやり直しが可能
長女の通っている定時制高校では「学びのやり直し」を掲げています。
勉強は高校に進学してからでもやり直せることが分かれば、将来に向けて自分のやりたいことや目的探しに時間を費やすことができます。
目標が見つかれば、何に対してどのような努力をすればいいのかが分かります。
高校卒業資格が必要ならば高校への進学、専門的な学科のある通信制高校で高校卒業資格と同時に技能を身に着ける等、一歩先へ目を向けた選択ができるようになります。
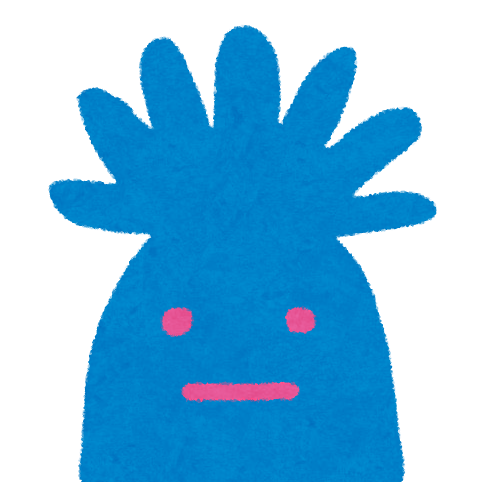
勉強をする手段を見つける?

夢を叶える手段として勉強する!
色々と試行錯誤してきましたが、同級生と同じ学力を維持しなければと焦る必要はなかったのだと思います。
頑張ろうと思える教科がひとつでもできたら、それを伸ばして自信に繋げていきましょう。



