こんにちは、おのやまです。
中学で不登校を経験した長女がおり、定時制高校に進学・卒業して現在は地元で働いています。
長女は小学生の頃から学校を休みがちで、中学2年の夏休み明けからほぼ学校に行けなくなってしまいました。
当時の私は学校に行かないのは悪いこと、不登校のままだと進学もできず将来の道も絶たれるのではないかという思い込みがあり、不安と焦りに追い立てられ子どもと自分を責める日々が続きました。
しかし不登校のままでも小中学校は卒業ができること、学校以外にも通える場所や支援があることを知っていれば、もっと落ち着いて行動ができたと後悔しています。
まずは誤った思い込みによる不安から自分を解放し、対策を考えていきましょう。
小中学校は出席日数に関係なく進級、卒業できる
これを知るだけでも「子どもを無理に学校へ通わせる必要はない」という安心に繋がると思います。
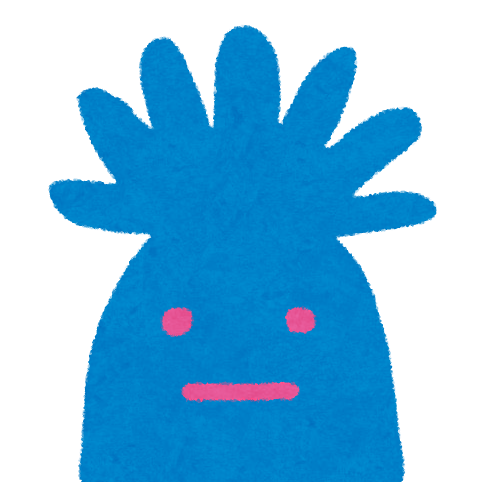
でも教育って日本の三大義務のひとつじゃない?
義務教育という言葉にこのようなイメージを持っている方はいないでしょうか。
- 教育を受けることが子どもの義務
- 子どもを学校に行かせるのは親の義務
私はまさにこの思い込みがあったためひどく悩みました。
しかし正しい意味を理解すると子どもを無理に学校に行かせる必要はないということが分かります。
子どもが教育を受ける権利
子どもに教育の機会を与える義務が親にある
保護者が子どもに教育を受けさせる義務=教育の義務になります。
子どもが学校に行くことを阻害する、教育を受ける機会を与えないといった行動をとる保護者が違反に該当します。
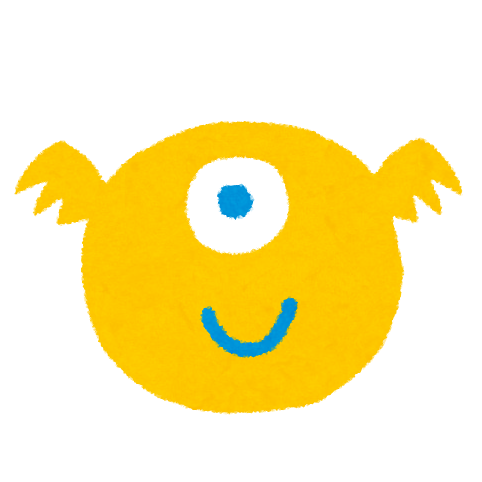
コロナ禍をきっかけに不登校の子どもは増え続け、具体的な対策が取られるようになってきました。
学校外での施設における指導でも、一定の要件を満たしている場合は出席扱いとして認められます。子どもに合った場所を見つけ、勉強や学校との繋がりが保てる状態を目指していきましょう。
学校に通える可能性が残っている場合の「相談室登校」
長女はいわゆる「さみだれ登校」状態の時に、自分のクラスではなく学校内にある相談室に登校していました。
相談室に常駐している先生はいますが、生徒は基本自習です。
週に2,3日程度の登校がしばらく続いたあとは再び通えなくなってしまい、学校の代わりに通える場所を先生から提案されました。
- 民間の私立校
- フリースクール
- 適応指導教室
相談室に設置してあるパンフレットや先生のお話等を参考に子どもにあった場所を探し、長女は市の教育支援センターが管轄している適応指導教室に通うことにしました。
学校との繋がりが保てる「適応指導教室」
適応指導教室は教育支援センターの管轄で学校との間で生徒の情報を共有し、適応指導教室に行けた日は学校での出席扱いとなります。
学校という組織、集団生活、人間関係になじめないことで不登校になってしまった子どもの場合、環境を変えることによって自分のペースや目標を取り戻していける可能性があります。
学校と家庭の間に教育支援センターが入ることによって連携が深まり、孤立してしまう不安もなくなります。
まずはどこに相談すればよいか?
相談室には不登校の生徒用に私立校やフリースクールのパンフレット、適応指導教室のリーフレットが置いてあったので、まずは学校を通して情報を入手しました。
適応指導教室に通いたい場合は先に学校に希望を伝えてから教育支援センターへ相談に行くと話がスムーズに進みます。
学校側はどうすれば生徒がまた元のように登校できるかに重点を置き提案や対策をしてきます。もし子どもが学校生活自体を苦痛に感じているのなら無理をせず、他の場所で学習したい旨を伝えるのがよいと思います。
不登校になってしまった子供が学校以外で通える場所
- 民間の私立校
- フリースクール
- 適応指導教室
- 出席扱い認定制度に対応している教材を利用した自宅学習

学校との連携ができない学習塾は除外しています
 出席扱い認定制度に対応したICT教材を取り扱っている通信講座
出席扱い認定制度に対応したICT教材を取り扱っている通信講座 適応指導教室は費用が一切かからず、在籍している学校と常に連携がとれるのでおすすめです。お住いの地域で運用されているか確認してみましょう。


