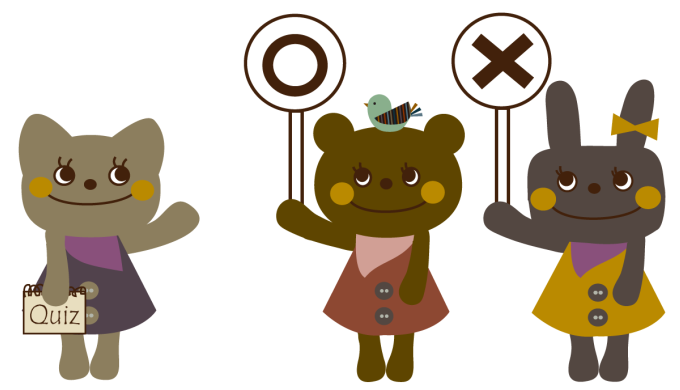こんにちは!おのやまです!
中学で不登校を経験した長女がおり、定時制高校に進学・卒業して現在は地元で働いています。
現在進行形で増え続けている不登校はテレビでも取り上げられることが多くなり、フリースクールや適応指導教室に関する内容も目にするようになりました。
こうした流れになる前、不登校の子どもが学校に行かずフリースクールに「逃げている」といったニュアンスの発言をした某市長が話題になりました。カリキュラムに則った指導ができない、親は教育の義務を果たしていないとも発言しており、「義務教育」というものを誤った認識で捉えている典型だと感じました。
「義務教育」という言葉からくる誤解
「義務教育」の言葉からくる間違った認識
- 教育を受けることが子供の義務
- 子供を学校に行かせるのは親の義務
おのやまも学生時代に覚えた日本の三大義務「義務教育」はずっとこの認識でした。
そしてこの間違った認識でいる人が某市長も含めて多いため、日本人の義務だからなにがなんでも学校に行って(行かせて)、学校で勉強しなければ(させなければ)ならないという誤った考え方に帰結してしまいます。
本来の義務教育の意味しているところは
- 子どもが教育を受ける権利
- 子どもに教育の機会を与える義務が親にある
子どもが教育を受ける権利を親が阻害してはならない(昔は子どもを学校に行かせず働かせていた時代があったため)という意味が根底にあります。
勉強をする場所は必ずしも学校に限定していません。
 不登校になってしまった子どもが学校以外で通える場所
不登校になってしまった子どもが学校以外で通える場所
フリースクールの存在
フリースクールというと民間で運営し必要経費がかかるイメージがありますが、学校の設置者である教育委員会が「教育センター」や「教育相談所」など相談窓口を設けて、教育支援センター(適応指導教室)を設置しているところがあります。在籍している学校と情報共有し常に連絡を取り合っているので安心です。
 適応指導教室ってどんなところ?
適応指導教室ってどんなところ?
不登校の原因が学校そのものであった場合、原因を突き止めようとしたり、無理をして通わせることに意味はありません。
登校できない子どもも、それを何とかしようとする親も不登校の状況が長引くほど疲弊していきます。
学校以外でも学べる場としてフリースクール、適応指導教室を子どもが自ら選択できる、学校が積極的に提案できる環境になってほしいと願っています。
不登校に悩んでいる人に見てほしい動画
学校行くのいやだな、つらいな、と思っている学生さんに向けた動画です。見ていておのやまも励まされました。